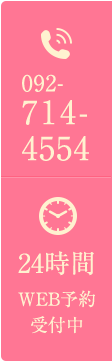この法律の内容は、「未成年者である子がその結果により影響を受ける手続きにおいては、子の意思を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない」というものです。
これは平成25年に施工された法律ですが、実務上(裁判所の取扱いにおいて)必ずしも普遍的に適用されていないことがあります。
未成年者である子がその結果により影響を受ける手続とは、親権や面会交流を定める調停や審判手続きが代表的なものです。従来、最高裁判所や多くの高等裁判所においては、子が10歳前後の事案においては子の意思を尊重すべきとされ、2~3歳児においては、客観的に判断すべきとされ、ていましたので、これを明文化したものと言えます。最高裁判所の考え方は、最高裁判所調査官による、長年の実務判断の蓄積によって築かれたものと思慮されます(当職は、最高裁判所の判断や判例変更は、最高裁調査官による実務調査の結果や助言によるところが大きいと考えています)。
これは、子がその結果により影響を受ける手続においては、子は夫婦間の紛争の第三者ではなく、当事者であるという発想が根源となります。実際、争いがある夫婦というか家庭においては、子が巻き込まれているのが実情です。その場合、子は一人の人格者として、その意思を尊重しなければ、決して子の福祉はまっとうされないということです。従って、その意思を問う前提として、その正しい判断を担保する前提として、子には、全ての事実関係を客観的に知らせる必要があると考えられます。
家庭裁判所に置いてある、子の面会に関する指導ビデオにおいては、子を夫婦間の争いに巻き込まないようにという指導が為されていますが、これは2~3歳までの子にはあてはまっても、それ以上の年齢の子は、既に当事者化している場合が多いので、あてはまりません。
子の意思を問う手段としては、調査官に依る、子に対する面談調査がありますので、これを求めることになります。多くの場合、夫婦は別居に至っており、子はいずれかの親と同居しています。また両親だけの主張からは、客観的な子の意思は判断できにくいので、客観的な子の意思は、専門家である調査官に依る面談が最適であると考えられます。両親だけの調査では、調査官や裁判官によっては、指導ビデオを根拠として、監護している親の影響であると決めつけ偏った指導が為される場合がありますが、その場合には、強く、客観的な調査を求めることが必要となります。
なお、子の意思は、監護親に対する忖度であっても、尊重されるというのが先例です。すなわち、子の意思は、必ずしも客観的な合理性に添うものとは限らず、親子の情も含めて子の価値観が尊重されるということです。